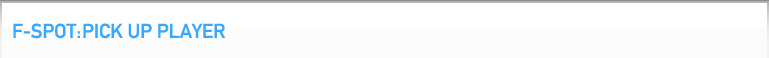![]() 2006/vol.08
2006/vol.08

 姉と弟ふたりを兄弟にもつ西山貴永は、幼少時代を宮城県仙台市で過ごした。サッカーを始めたのは小学校2年のとき。偶然が、彼のその後の人生を決めた。母親が西山の友人が入っていたサッカー少年団がなくなったと勘違いしたため、別のクラブに入ることになったのだ。だが、友人が通っていたのは、サッカー“教室”。西山が入ったのは本格的なクラブ。お遊びでやるか、本格的にやるか、このとき西山の方向性は定まったと言っても過言ではない。
姉と弟ふたりを兄弟にもつ西山貴永は、幼少時代を宮城県仙台市で過ごした。サッカーを始めたのは小学校2年のとき。偶然が、彼のその後の人生を決めた。母親が西山の友人が入っていたサッカー少年団がなくなったと勘違いしたため、別のクラブに入ることになったのだ。だが、友人が通っていたのは、サッカー“教室”。西山が入ったのは本格的なクラブ。お遊びでやるか、本格的にやるか、このとき西山の方向性は定まったと言っても過言ではない。
「なくなったのは勘違いだったんですけどね。でも、結局そのおかげでACクレックに入ることになったし恩師にも出会えました」
体は小さかったが、上級生にも平気でつっかかるような負けん気の強い性格だった西山は、入ってすぐに6年生とケンカをして半年ぐらいクラブに通うのをやめてしまった。それを引き留めたのが恩師である監督だった。
「練習試合にとりあえず出てみろって言われて。出たらやめようと思ってたんですよ。でもその試合でハットトリックしちゃって、監督が親に『やめさせないでくれ』って頼んでくれて、結局戻ることになったんです」
その後、中学時代は西山の父親や友人の父親たちが決起して、クラブチームを作ってしまう。1年生しかいないFC宮城は力をどんどんつけ、3年時には全国クラブユースでベスト8の成績を残す。このとき、ひとつの出会いがあった。日本クラブユースサッカー東西対抗、いわゆるメニコンカップで谷口博之とチームメイトになったのだ。
「いきなり、話しかけてきたんですよ。当時のタニは坊主で小さかった。僕と同じぐらいでしたね。面白いやつだなぁと思ったので覚えてるんですよ」
夏の大会が終わると、西山のもとには4チームほどJクラブユースからオファーが舞い込んだ。ほかにも地元の強豪・仙台育英に進学するという選択肢もあった。両親は西山に「自分が考えた進路でいいから」と、告げた。広島へいく決断を伝えたとき、友人たちは「お前が人一倍サッカーを真剣にやってるのはわかってる。応援してるぞ」と言ってくれた。
 15歳の春、広島に単身渡った西山は当然のようにホームシックにかかった。宮城県から広島へという距離の遠さだけでなく、言葉の違いから寮の規律ある生活までなにもかも初めて体験する出来事だった。
15歳の春、広島に単身渡った西山は当然のようにホームシックにかかった。宮城県から広島へという距離の遠さだけでなく、言葉の違いから寮の規律ある生活までなにもかも初めて体験する出来事だった。
「まず、授業が広島弁ってことにカルチャーショックでした。小学生のときに関西では教科書も関西弁なのかなぁって素朴な疑問を抱いたことがあって(笑)、でも実際は標準語だったから違うのかと思ったら、バリバリの広島弁でノイローゼ気味になりました。キツいんですよね、言葉が。慣れてないからビックリしました。寮生活は、朝7時に起きて掃除してご飯食べて学校行って練習して風呂入ってご飯食べて10時30分には携帯を集めて11時に就寝。毎日、その繰り返しでした」
何回も家に帰りたいと願ったことはあった。でも、西山を思いとどまらせたのは家族の存在、とくに辛いときには祖父母の顔が思い浮かんだ。
「おじいちゃんとおばあちゃんは、もともとサッカーが好きじゃなかったんです。でも、小学校の時、僕の試合をみにきてくれてサッカーが好きになってくれたことがすごくうれしかった。ユースのときも東京から広島まで必ず試合を観に来てくれてたんです。だから頑張れました」
家族以外に一番身近で支えてくれたのは、厳しくも温かく接してくれた寮長さんと寮母さんだった。
「それまでお母さんに甘えていた自分がひとりで生活しなきゃいけない。ひとりの人間として自立できるようにきちんと指導してくれました。問題児で、怒られてばかりでしたけどね。洗濯して置きっぱなしにしても、ご飯を食べなくても、寝坊をしても怒られた。だからこそ、僕のプロ初試合を広島でやれて、観にきてくれたことはすごくうれしかったんです。アウェイの広島戦で自分がサッカーをする姿をみせることができて…」
2006年4月8日(土)、J1リーグ第7節、懐かしい広島ビッグアーチのピッチに西山は立っていた。スタンドには、両親、祖父母、ユース時代の寮長さん、学校の先生らが駆けつけていた──。


ここにくるまで2年間を要した。高校3年の12月、練習試合形式のセレクションでフロンターレのテストを受けた西山は、その数日後に吉報を受けた。
「学校にいるときに広島ユースの森山監督から電話があって、担任に放送で呼び出されたんです。ドキドキしながら部屋に行ったら『受かったぞ』って言われて、うれしくて先生に電話を借りてすぐ親に電話したんです。そしたら『知ってるよ』って。森山監督がうれしくて僕より先に親に報告してたんですよ」
フロンターレに加入してからは、得意のドリブルには手応えを感じていたものの、判断のスピード、90分の時間配分、連携面、あらゆる面でのステップアップの必要性を痛感した。
「単純に体がぶつかったらダメなので姿勢を低くして踏ん張れる状態をコーチに教えてもらいながら、まずは体の使い方を覚えていきました」
 2年目にサテライトリーグに参加できるようになると、それまでは気が向かなかった与えられたサイドのポジションにも真剣に取り組めるようになった。攻撃的なポジションしかやったことのなかった西山にとって、守備への戸惑いは大きかった。後ろの選手からの指示がなければ、どこに動くべきかさえもわからなかったという。
2年目にサテライトリーグに参加できるようになると、それまでは気が向かなかった与えられたサイドのポジションにも真剣に取り組めるようになった。攻撃的なポジションしかやったことのなかった西山にとって、守備への戸惑いは大きかった。後ろの選手からの指示がなければ、どこに動くべきかさえもわからなかったという。
とりあえず、紅白戦で対面になる森勇介を手本にした。西山は森と対峙して、「日本一の右サイドの選手だ」と感じていたからだ。最初は森相手になにもできなかったが、少しずつ駆け引きができるようになることが自分のスキルアップのバロメーターになった。西山の成長について森は、こう語る。
「ポジショニングがよくなった。とくにボールをもらう位置が前とは全然違う。あいつは体は小さいけど強いし、スピードもある。それを活かしていけばまだまだ伸びると思う」
そして──。
チャンスは突然訪れた。
プロ初出場は、ケガ人が続出したチーム事情で、気づいたら手にしていた。前日にはあった緊張感が、試合当日にはまっさらに消えていた。選手入場のとき、感極まって泣きそうになった。西山は、ピッチに立てる喜びを表現するかのように積極的に仕掛けていった。対面となったのは広島ユースの先輩でもある駒野だった。そして、1点リードで迎えた13分、左サイドで粘り強くキープした西山からボールは同期加入の谷口へ渡った。「入ってくれ!」と願った西山の気持ちを乗せるかのように谷口が放った強シュートは弧を描いてゴールマウス右上へと突き刺さった。
試合後も麻生グラウンドでも初出場の感想を尋ねられた西山は、開口一番、「気持ちよかった」と充実感を表現した。
そして9月3日(日)ナビスコカップ準決勝、ホームにジェフ千葉を迎えた一戦でフロンターレは1対2とビハインドのまま時計は45分を指そうとしていた。きょうは、もう呼ばれることは絶対にないな、と西山はアップの足をとめて、せめて引き分けてくれないかと願って試合の行方を見守っていた。
「ニシ!」
関塚監督が西山を呼び寄せた。
「ボールもったら縦に勝負しろ」と言われ、西山はピッチに送り出された。西山は、とにかく強引に前へ進んだ。そして、西山のドリブルからコーナーキックのチャンスを掴んだフロンターレは、引き分けに追いついた。
「ああいう状況で使ってもらえたのはうれしかった。いまはベンチに入れるか入れないかギリギリの状況だけど、まずは常にベンチに入って、流れを変えられる選手だと認めてもらえるようになりたい」
試合後、ミックスゾーンで選手達が取材を受けるなか、西山がするりと人垣を抜けていった。今野が「きょうは、ニシがヒーローなのにね」と後に続いた。チームメイトに「お前が流れを変えたな」と言われたことが西山はうれしかった。
西山がドリブルを開始すると、なにかが起きる予感がスタジアムを包み込む。それが、彼の最大の魅力だ。足に吸い付くようにボールが絡みつき、小さい体で敵をなぎ倒していくような、そんなイメージだ。
「僕、サッカーやってるときは自分が小さいことを忘れちゃうんです。全然気にならないし。ふとショーウィンドウとかに映る自分を見て、『あれ、オレって小さいんだ』って気づくんですよね」

![]()
2004年、サンフレッチェ広島F.Cユースより川崎フロンターレに加入。重心低いドリブル突破を武器に攻撃的なサイドアタッカーとして成長著しい選手だ。1985年7月11日生まれ、宮城県仙台市出身。