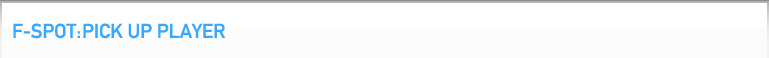2011/vol.04

ピックアッププレイヤー:柴崎晃誠
繊細かつ柔らかなタッチで操るボールコントロール。左右両足から繰り出せる正確なパスと高精度のミドルシュート。そして尽きることのない、圧倒的な運動量。今シーズンより加入した柴崎晃誠が、フロンターレの中盤に新しい風を吹き込んでいる。4シーズン慣れ親しんだ東京ヴェルディを離れ、新天地に挑む覚悟がそこにはあった。
 柴崎晃誠の歩んできたサッカー人生を辿ってみると、最初に目を引く経歴は、やはり出身高校だろう。長崎県立国見高等学校──いわずと知れた全国高等学校サッカー選手権大会の超強豪校である。だが、その前に書かれている出身中学校が興味深い。国見町立国見中学校──そう、彼は国見で生まれて国見で育った、生粋の「国見っ子」なのである。
柴崎晃誠の歩んできたサッカー人生を辿ってみると、最初に目を引く経歴は、やはり出身高校だろう。長崎県立国見高等学校──いわずと知れた全国高等学校サッカー選手権大会の超強豪校である。だが、その前に書かれている出身中学校が興味深い。国見町立国見中学校──そう、彼は国見で生まれて国見で育った、生粋の「国見っ子」なのである。
「確かにあまり多くないかもしれませんね。ただ自分の代だと、渡邉大剛もそうなんですよ。あとひとつ上の学年には徳永悠平もいますよ。悠平くんとは家も近所で同じ小学校でした」
国見町(現・雲仙市)の人口は、1万人たらず。畑や田んぼが多く、柴崎は外でよく遊ぶ活発な少年だった。町ぐるみで力を入れているスポーツは、もちろんサッカー。ならば、すぐに「ボールと友達」になったことだろうと思ったのだが、物心ついて最初に熱中した遊びは、意外にも「ビー玉」だった。
「ちゃんと遊び方かあるんですよ。まず小さな十字になるように地面に何点か穴を開けるんです。そしてそこを狙って順番にビー玉を転がして入れる・・・入った穴の場所によって『天国』と『地獄』があって、それをみんなで競うんです。そのとき、近くに転がっていた人のビー玉を弾き飛ばせば、それを取れるんですよ。あれはハマリましたね。何て呼ぶ遊びなんだろう?『ビー玉やろうぜ』って言ってました(笑)」
相当に楽しかったのだろう。日ごろは落ち着いて話す柴崎が、必要以上に熱っぽく説明してくれたのがなんだか面白かった。そんな「ビー玉小僧」は、4つ上の兄に誘われたのがきっかけで「サッカー少年」となっていく。小学一年生から地元の国見少年サッカークラブに入ると、夢中になってサッカーボールを追いかけた。パス、ドリブル、フェイント・・・自分がサッカーをする上で大事にしている技術の基礎は、すべてここで身に着けたものだ。ボールテクニックを磨いてはミニゲームで試し、町内でリフティング大会が開催されれば上級生に混じって出場した。小学3年生のときには、Jリーグが開幕した。当時のアイドルは、なんといっても三浦知良。カズのまたぎフェイントを真似ながら、練習にあけくれる毎日を過ごしていた。


そういえば、柴崎晃誠がプロ入りした当時、東京ヴェルディの関係者からは「ボールを持ったときの立ち振る舞いがいい」という評判をよく耳にしたものだ。いわゆる「雰囲気を持っている」というやつである。感覚的な言い回しではあるが、確かにピッチでボールを持ったときの佇まいには、スケールの大きさを感じさせる魅力がどことなく漂っていた。それは「両足でボールを操れる柔らかなタッチ」であり、「中盤でルックアップしたときの姿勢」といった要素によるものだと思うのだが、こういった原点もこの時期に形成していったのかもしれない。そして国見中学を経て、国見高校へと進学する。
「練習は本当にきつかったですね。とにかく、走りますから。とりあえず『この3年間はしのごう、なんとか乗り切ろう』って思いながら練習してました。毎日それしか考えてなかった」。
国見高校といえば、その練習量の多さはあまりに有名だ。なかでも走り込みの量がケタ違いであることでよく知られている。とにかく、信じられないような距離を徹底的に走らされた。そして練習が終わると、多くの部員が寮に戻る中、自宅通学の柴崎は10分ほど自転車を走らせて帰路に着くのである。猛練習でクタクタになった身体に鞭打ってペダルをこぐのはさぞかしキツかっただろうと思ったのだが、「これで帰れるんだと思うと、その開放感からむしろ元気が出ていましたよ」と本人は笑顔で話す。スピードを上げて浴びる、強くて冷たい向かい風が疲れきった身体にはたまらなく心地よかった。
柴崎は、自身の座右の銘として「継続は力なり」をあげている。高校時代の恩師・小嶺忠敏総監督(当時)からのその教えを今も一番大事にしている。それは継続によって生まれる力の大きさを実感しているからだ。「毎日走っていたので、体力は自然につきますよ。そして体力では絶対に負けないっていうのが、試合での強みにもなっていましたね」。現在の持ち味の一つにある「圧倒的な運動量」も、この国見時代に培ったものである。継続は力を生み、そしてそれは実を結ぶことも体験を通じて学んだ。
![]()
 高校時代は、選手権で2年連続優勝を果たしている。2年次にはMFながら6ゴールをあげて、大会得点王に輝く。ポジションはトップ下。裏に走りこむ仕事だったが、それほどゴールを期待されていた役割ではなかった。しかし大会が始まると、なぜかゴール前で絶好のボールが自分の前にこぼれてきた。「こぼれ球とかごっつあんゴールばっかりだったんですよ。ラッキーでした」と本人は話すが、継続は幸運も引き寄せるのかもしれない。
高校時代は、選手権で2年連続優勝を果たしている。2年次にはMFながら6ゴールをあげて、大会得点王に輝く。ポジションはトップ下。裏に走りこむ仕事だったが、それほどゴールを期待されていた役割ではなかった。しかし大会が始まると、なぜかゴール前で絶好のボールが自分の前にこぼれてきた。「こぼれ球とかごっつあんゴールばっかりだったんですよ。ラッキーでした」と本人は話すが、継続は幸運も引き寄せるのかもしれない。
そして3年次、戦後史上初となる大会3連覇に挑んだ。決勝の相手は千葉の強豪・市立船橋高校。柴崎の言葉を借りれば、絶対に負けたくないとチーム全員で団結していた「見かけがチャラチャラしたような集団」だった。しかし市船は手強かった。市船には現在のチームメイトである小宮山尊信もいた。
小宮山が当時のことを証言する。
「国見の選手たちが『チャラチャラしてる相手に絶対に負けたくない』と言っているのは聞いていました。でも僕らも『坊主頭には絶対に負けない』って思ってやってましたから(笑)。国見とは練習試合も含めて何度か対戦していたので、お互いに知り尽くしている相手だったと思います。晃誠の印象ですか?抜群にうまかったですよ。攻撃には必ず絡んでくる選手だったので、守るほうとしては、すごくやっかいな相手でした」
勝敗を分けたのは、高校サッカー史に残る1本のロングシュートだった。0-0で迎えた後半20分。FKのこぼれ球に小川佳純が走り込み、30メートルの弾丸シュートを国見のゴールネットに突き刺した。この一発に沈み、国見3連覇の夢は絶たれた。
「あの1発は忘れられないですね。すごいシュートでした。あとは悔しかったことしか覚えていないです。サッカーをしていて、初めて泣きました」。
こうして柴崎の高校時代は幕を閉じた。

高校卒業後は、国士舘大学に入学した。プロ入りの話もあったが、小嶺総監督に相談して決めた進路だった。
「プロにはなりたかったし、その選択もありました。ただプロになっても、すぐに通用するとは限らない。サッカー人生は短いかもしれないけど、人生は長いですから」
大学時代には、養父雄仁とダブルボランチを組み、中心選手してチームをけん引した。とはいえ、サッカー漬けだった高校時代の反動もあったのだろう。サッカーに対する情熱は変わらなかったが、東京での大学生活で、少しだけネジを緩めてしまったことも否定はしなかった。「羽を伸ばした部分はあったかもしれませんね。ちょっとサッカーもおろそかになった。高校卒業してJリーグに行った大剛(渡邉大剛)が活躍したニュースを見て、自分もプロにいっていればよかったかなと思ったときもありましたよ」。それでも多くのスカウトが熱視線を送る逸材であることには変わりなかった。庄子春男強化部長も、大学時代から注目していた選手だったことを後に明かしている。
柴崎は、大学在学中に練習参加していた東京ヴェルディ1969(当時)に入団を決めた。
2007年、プロサッカー選手としての日々が始まった。
東京ヴェルディはJ2のカテゴリーに所属していたが、チームはJ1昇格を至上命題に掲げ、フッキ、ディエゴ、名波浩、服部年宏、土屋征夫・・・J2とは思えない超大型補強を敢行して臨んでいた。その指揮を執るのはラモス瑠偉。強烈な個性派集団だったと言ってもいい。このそうそうたる顔ぶれとともに新加入選手会見に同席していたときの不安な気持ちを、苦笑いして告白する。
「本当に凄い人たちばっかりで、自分は無理だろって思ってました。実際に練習で一緒にやってみて・・・やっぱりちょっと無理だなって思いましたね」
プロの世界で面を食らったのが、スピードだ。プレッシャーのスピード、攻撃のスピード、なによりも判断のスピード。すべてのスピードが、これまで味わった世界とはまるで違う次元のものだった。大学時代はボールを持ってからのプレーに十分な余裕があったが、その感覚がここでは通用しなかった。早い判断を下し、早くボールを動かし、そして自分も早く動かなければ、あっという間に距離を詰められ、ボールをかっさらわれた。
プレイヤーとして強烈なインパクトを受けた選手もいる。川崎フロンターレから期限付き移籍で加入していたフッキだ。
「衝撃を受けましたね。今振り返っても、これまで見てきたFWの中で一番じゃないですか。どこがすごいかですか?スピード、シュート、体も強いし・・もう全部すごかった。しかも自分よりも年下(笑)」
後にヨーロッパでも活躍することになる怪物ストライカーである。その規格外のパワーを備えたプレーを目の当たりにして、ただただ圧倒された。こんな人間とずっと勝負していかなければならないのかと思うと、不安は大きくなるばかりだった。

だが柴崎のJリーグデビューは、意外にも早いタイミングでやってくる。
チームの中核を担っていたのは経験豊富なベテランだったが、その反面、同期入団の明治大卒・福田健介を開幕戦で先発起用し、同じく法政大卒の井上平を途中出場させるなど、ラモス監督は若手の抜擢にも積極的だったのだ。そして柴崎にも出場機会が巡ってきた。
4月22日に行われたJ2第10節コンサドーレ札幌戦。
札幌ドームで行われたこの試合にメンバー入りした柴崎は、ベンチから試合を見守っていた。ただこれが、まれに見る壮絶な一戦となる。まずセットプレーを中心に札幌が立て続けに得点し、開始わずか16分の時点でスコアは3−0。だが東京Vも、ここから怒涛の猛反撃を見せ、3点差を同点に追いつく意地を見せるのである。ところが64分、カウンターからダヴィの突破を止められず失点。4-3となり札幌に再びリードを許してしまう状況となる。この展開で、77分、柴崎に出番が訪れるのだ。待望のデビューの瞬間。ただ本人にとっては、「寝耳に水」ともいえる出場だった。
「最初、一柳(夢吾)が出るはずで、彼が準備していたんですよ。そうしていたら、急に『コーセイいくぞ!』って言われた。だから、あのときは心の準備が全然できていなかったです。攻撃に絡むように言われたのですが、ほとんど絡めなかった。何もしていないですし、芝で転んだことしか覚えていない・・・デビュー戦といっても、全然充実感はなかった」
プロとして最初のキャリアを刻んだゲームにも関わらず、なんともそっけない感想だが、記憶に残らないのも無理はないのかもしれない。当時の試合映像を見直してみたのだが、ボールのある場面に柴崎が出てくることはほとんどなかったからだ。実はこの試合の記憶を手繰り寄せてもらうまでにも、かなりの時間を要している。当時の新聞記事や公式記録を見ながら、やっとのことで記憶の糸を手繰り寄せてもらったほどだった。苦いプロデビュー戦だった。
結局、試合は3−4のまま敗れ、チームは4連敗を喫した。その2試合後の鳥栖戦でも柴崎は途中から出場しているが、それを最後に、シーズン終盤まで出番自体がまるでめぐってこなくなる。ベンチにも入れず、スタンドから試合を観戦するという苦しい時期がずっと続いた。
「試合にも全然絡めなくて・・・チームの紅白戦にも出てませんでしたからね。毎日練習ばっかりでした。サテライトの選手は、トップとは別に人工芝のグラウンドでやることが多かったんですけど・・・もうダメだと思いましたね」
高校、大学とチームの中心選手であり続けてきた柴崎にとって、試合に出られない練習の日々は精神的につらかった。しかしそんなとき、決まって雰囲気を盛り上げる選手がいた。名波浩だ。チームが戦い方を変えたことで指揮官の構想から外れ、Aチームとは別の練習が多くなっていたが、それでも率先して若手に声をかけ、手を抜かずに取り組む姿勢でチームを支える役割を全うしていた。
「名波さんがよく言っていたのは、『試合に出れなくても練習はしっかりやれ』ということでした。頑張って練習をやっていれば、必ずいい結果がついてくるから、ってことですよね。要は、腐るなってことなんですけど、名波さんからそんなことを言われたら・・・やるしかないですよね」

腐らずに練習に取り組む姿勢。その継続が力になった。そしてチャンスも運んできた。昇格レースの佳境を迎えた第45節湘南戦で、待望のベンチメンバー入りをすると、第46節山形戦では途中出場を果たすのだ。柴崎にとっては、約半年ぶりとなるリーグ戦出場だった。その後もコンスタントにベンチメンバー入り。後半の難しい時間帯に途中投入されても、新人らしからぬ落ち着いたプレーでゲームを引き締め、ラモス監督からは「サッカーをよく知っている選手」と賞賛された。
「最後に少し出て、何かがつかめたのかもしれませんね」
チームは見事にJ1昇格を達成した。自分の中で、ほんの少しだけの手ごたえを感じて、柴崎晃誠のルーキーイヤーは終わった。
2008年。東京ヴェルディにとって3年ぶりとなるJ1での戦いが始まった。
シーズン前、首脳陣から高い評価を受けた柴崎は、背番号「8番」をつけることになった。クラブにとっては北澤豪が付けていたことで知られる伝統ある番号だ。彼にそれだけの多くの期待を寄せていたという現れでもある。
「あんまり意識はしたくなかったですね。プレッシャーを感じる重い番号ですから。それに、あのときの自分なんてまだまだだと思っていました」
 スタートこそ出遅れたが、第15節ジェフ千葉戦でJリーグ初ゴールを記録すると、夏以降にはスタメンとして定着するなどチームでの居場所を見出していた。だが柱谷監督のチーム作りには暗雲が立ち込めていた。開幕直後に川崎フロンターレを退団し、電撃加入したフッキが夏には再び欧州へ移籍した影響もあり、チームは何度も軌道修正を余儀なくされていたのだ。そこに「継続」はなかった。ついには残留争いから抜け出せずに最終節を迎えることとなった。勝てば残留の決まる状況ではあったが、相手は優勝の可能性を残す川崎フロンターレ。柴崎はこの大事な一戦を先発で出場した。
スタートこそ出遅れたが、第15節ジェフ千葉戦でJリーグ初ゴールを記録すると、夏以降にはスタメンとして定着するなどチームでの居場所を見出していた。だが柱谷監督のチーム作りには暗雲が立ち込めていた。開幕直後に川崎フロンターレを退団し、電撃加入したフッキが夏には再び欧州へ移籍した影響もあり、チームは何度も軌道修正を余儀なくされていたのだ。そこに「継続」はなかった。ついには残留争いから抜け出せずに最終節を迎えることとなった。勝てば残留の決まる状況ではあったが、相手は優勝の可能性を残す川崎フロンターレ。柴崎はこの大事な一戦を先発で出場した。
「あのときのフロンターレの印象ですか。とにかく攻撃陣が強いチームですね。ジュニーニョ以外にもブラジル人がいたような気がします・・・レナチーニョか。ただあの試合は、福西さんが退場して、すぐにこっちが10人になってしまったんですよね。残留がかかっていたので、相手とか試合内容よりも、とにかく自分たちが必死だったことしか覚えていないですよ。最後に憲剛さんにゴール決められたのは覚えています」
前半は10人で必死に耐えたが、64分にサイドを崩されて、レナチーニョのゴールで失点。だが同時刻にキックオフしている他会場では、残留を争うライバル・ジェフ千葉がFC東京に0-2とリードされていた。このまま終われば、仮に負けても残留が決まる状況だった。ところが終盤、千葉が2点差をひっくり返す逆転劇を見せたことで事態は急転直下。勝たなければ、自動降格になってしまう状況に追い詰められたのだ。83分にベンチに下がった柴崎は、祈るような気持ちで10人で戦う味方に願いを託したが、フロンターレは強かった。ロスタイムには中村憲剛の豪快なミドルシュートが突き刺さり、万事休す。そして千葉が4-2でFC東京に勝利。自動降格という最悪のシナリオで、チームはわずか1シーズンでJ1の舞台から去ることになった。
「J1でやれなくなる悔しさもあったし、自分の力のなさもすごく感じた」
試合後のベンチで、柴崎はサッカー生活二度目となる涙を流していた。
 2009年シーズン、再びJ2での戦いが始まる。
2009年シーズン、再びJ2での戦いが始まる。
この年から柴崎はチームの中盤をけん引するようになるのだが、その影には一人のストライカーの存在があった。
大黒将志である。
08年の夏に加入した、日本代表経験もあるこのFWは、フッキのように圧倒的な個人技で局面を打開していくタイプではない。相手守備陣との駆け引きを繰り返しながら、オフ・ザ・ボールでの動き出しでパサーに生かされるストライカーだった。ゴールを奪うためには、阿吽の呼吸を持つパートナーが必要だったのだ。そこで柴崎のパスセンスに白羽の矢を立てたのである。大黒は、練習で柴崎のプレーを見たときに「コイツはパスが出せるな」と感じたという。
「要は、ボールを持ったときに顔が上がっているかどうかなんですよ。そしてターンができるかどうか。できない選手はすぐ後ろを向いてしまう。自分が点を取るには、パスを出せる人が必要やし、晃誠はそういうタイプやった」
大黒からのレクチャーが始まった。例えば、シーズン前のキャンプ中のある練習試合後、大黒からこんな風に声をかけられている。
「なんであのとき、パス出せへんかった?おれ、フリ−だったやん」
「いや、フリーじゃなかったですよ。だから出せなかったです」
「そんなら、ちょっと一緒にDVD見ようや」
そのまま部屋に行き、終わったばかりの練習試合のDVD映像を見ることになった。大黒がその場面を一時停止して説明する。
「こういう場面は、俺の感覚だとフリーやから。ここでポンとここに出せ。このタイミングでな」
そういう感覚だったのかと、目からウロコが落ちる思いだった。
「新鮮でしたね。自分がいかに見えてなかったか、気づかされました」
大黒に言われたことを実行し続けることで、柴崎は自分の中に変化が起こり始めていることを実感した。
「変わりましたね。それまでは、横パスや後ろへのパスが多かったけど、前を向いて出すことを意識するようになった。そして自分がボールを持ったときに走るからと大黒さんに言われていたので、自分からボールをもらいにいくようになりました」
大黒が柴崎に要求していたことは一貫していた。
「晃誠には、ミスってもいいからまずは前を向けと。そしてターンをしろと言いました。それでミスしたら、今のはアカンタイミングやったんや、とか学べるじゃないですか。バックパスしても何も生まれないなんだから。ターンして俺が走ったのが見えたら、どんどんパスを出せ。そこから自分も飛び出していけと言い続けました」
もともとは攻撃するのが好きな選手だ。運動量にも自信がある。自分を生かしてくれる大黒とのホットラインを確立させながら、自らも中盤の底からどんどんゴール前に顔を出すことを意識し続けた。そして継続は形になる。その年、柴崎は7ゴールという結果を記録した。なによりも、自分のプレースタイルに幅が広がっていくのを感じた。
あるとき、「大黒さんの教えで、柴崎晃誠がよくなっていますね」と水を向けると、「ふふふ。俺、見る目があるんでね。それにアイツはできるヤツやから」と不敵に笑っていた大黒将志の姿をよく覚えている。
2010年になると、東京ヴェルディは完全に「柴崎晃誠のチーム」としてカスタマイズされていた。
川勝監督は柴崎を中心にしたチーム作りを公言し、その言葉を裏付けるように、リーグ戦では出場停止の1試合を除いた35試合に出場。チームは昇格を逃したが、存続危機で揺れる中、堂々たるパスサッカーを展開して周囲を魅了した。そしてその攻撃は、すべて柴崎を経由して始まっていたといっても過言ではなかった。


そんな彼を周囲が放っておくはずもない。契約切れとなるシーズンオフには、複数のJ1クラブから熱烈なオファーが届いた。獲得を打診されたクラブ関係者と話をしようと喫茶店に入ると、監督が同席しており、直々に口説かれたこともあった。自分を高く評価してもらえるのはプロとして嬉しいことだが、その反面、「なんで?俺のどこがいいんだろう?」ととまどう気持ちもあったという。初めて経験する移籍に対する不安もあった。新しい世界に挑戦したい意欲もあるが、新しいチームになれば、今までの自分のプレーができるとは限らない。当然、そこにはリスクも伴う。ヴェルディも自分を必要としており、強く残留を要請してくれているだけに、すぐには結論を出せずにいた。
川崎フロンターレも、柴崎争奪戦に名乗りを上げている。ゲームを作れる若手ボランチはチームの大きな補強ポイントだったからだ。東京ヴェルディの強化部に在籍経験のある西澤淳二スカウトは、柴崎晃誠のよさを深く知り、そして彼の能力を高く評価していた人物である。
「中盤の底で起点になれること。プレッシャーを受けた状況でも、しっかりターンできる選手なのは魅力でしたね。そしてそこからゴール前に入っていける動きもある。左と右も両足使えて、ミドルシュートも高い決定率を持っている。相馬監督はパスサッカーを志向していましたし、引かれた相手をどうこじあけるかというときに必要になっている。本人もJ1で勝負したいという気持ちを持っているようだったし、そういう選手が入ってくることで、チームもまた活性化していけますから」
交渉の席での柴崎との感触は悪くなかったが、複数のクラブとの競合だ。当時、勝算はあったのかと庄子強化部長に聞くと「こればっかりは、どうなるかわからないからね」との本音を明かしている。ただ、交渉の場で柴崎本人に伝えた言葉があった。
「ウチでレギュラーを取れれば、そこから上も狙えるぞ」
ここで言う「そこから上」というのは、日本代表のことを指す。
柴崎には、人生における重大な決断を下すときに心がけていることがあった。信頼できる人の意見をしっかり聞くことだ。高校卒業後、プロか進学かで悩んだときは、恩師である小嶺総監督の言葉に耳を傾け、結論を出した。公私共に尊敬してやまない飯尾一慶に相談すると、ストレートにこう言われた。
「どれを選んでも、行って後悔だけはするなよ」。
彼には「日本代表になる」という思いがあった。J2の舞台では、なかなか身近に感じられることの出来なかった目標を実現するなら、このクラブで勝負するしかないと思った。そして2010年12月11日、柴崎晃誠は4シーズン慣れ親しんだ東京ヴェルディを離れ、川崎フロンターレへの移籍を発表した。
「みんなの能力が高いなかでやれることが、自分の成長につながると思いました。憲剛さんや稲本さんなど、日本代表を経験している選手と近くでやれることで、いい刺激を受けることができる。自分が持ってないものを盗みたいという気持ちもありましたね。なにより、フロンターレで試合に出れば、日本代表に近づけると思った」
2011年、すでにシーズンは動き出している。初めての移籍。そして3年ぶりとなるJ1での戦いだが、開幕戦から先発として定着し、中村憲剛、稲本潤一にも気後れすることなく、中盤のレギュラーとして堂々と君臨している。だがその挑戦はまだ始まったばかりだ。
チームにタイトルをもたらす。
そして日本代表になる。
継続は力を生み、そして必ず実を結ぶ。柴崎晃誠はそれをフロンターレで証明する。

profile
[しばさき・こうせい]
中盤での組み立てと献身的な守備でチームを引き締めるゲームメーカータイプのMF。強烈なミドルシュートも武器。年々パフォーマンスの安定感が増してきており、今年は新天地で激戦区の中盤レギュラー争いにチャレンジする。1984年8月28日/長崎県雲仙市国見町 生まれ。
>詳細プロフィール