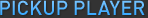熱く、強く。
MF5/谷口彰悟選手
テキスト/いしかわごう 写真:大堀 優(オフィシャル)
text by Ishikawa,Go photo by Ohori,Suguru (Official)
今シーズン、ベガルタ仙台から川崎フロンターレの一員となった角田誠。忘れられない東日本大震災を経て、
31歳にして飛び込んだ川崎という新天地。その道のりと抱え続けている思いに迫った。

2015年3月7日。今季の開幕戦となった横浜F・マリノス戦。
身体の芯まで冷えるような寒さの中で、フロンターレのユニフォームをまとった角田誠はプレーしていた。
前半22分。小林悠のゴールで2対1とリードすると、選手達は再開するまでのわずかな時間の話し合いで、フォーメーションを変更している。その輪の中には角田誠もいた。失点場面も含め、守備の局面でシステム上の齟齬が起きていたため、ピッチ上の違和感を解消しようとする狙いだった。具体的には、左ウィングバックの車屋紳太郎を最終ライン下げることで3バックから4バックにし、右ウィングの小林悠を中央にした大久保嘉人との2トップへの変更である。この狙いは奏功し、チームは再び循環。3対1で開幕戦の白星を飾ることに成功した。
「2点目が決まった時、カク(角田誠)が後ろで感じていたことやヨシト(大久保嘉人)が前で感じていたことも聞いて、後ろを4枚に変えた。カクは状況も読めるし、存在としても大きい。同じメンバーでも形を変えられるし、彼の懐の深さがチームに良い影響を与えている」
試合後、あのときのコミュニケーションの中心にいた中村憲剛は、システム変更の背景には今季加入した角田誠の柔軟性があったと明かしている。そして味方の尻を叩きながら、チーム全体を仕切れるセンターバックは中村が望んでいた存在でもあったからだ。
「今までは自分とヨシトだったり、前の選手がそういう役割を担っていたから。カクは自分よりも後ろだから、全体像をみてくれるし、自分の尻も叩いてくれる。例えばプレスの掛け方も、いくところといかないところも早めに判断してくれる。去年まではジェシがいたけど、言葉の細やかさや、声で動かす部分でどうしても難しかったから、そこをダイレクトにピッチに反映できる日本人が後ろにいるのは大きいよ」
開幕戦から大黒柱の中村が信頼を寄せるほど、角田誠というピースはしっかりハマった。ただ移籍して来た当初は練習から緊張の連続だったという。キャンプの時期を、苦笑いを浮かべながら振り返る。
「頭が疲れましたね。特にキャンプのときは、クタッっとなってました(笑)。ボール回しの練習でも、『ボールが来るときの判断をどうしよう?』とか『どこに出したら良いんだろう?』と常に緊張していた。ミスしないように安全なプレーばかりしていてもダメだし、慣れるまで大変でしたよ」
とりわけ面を喰らったのは、風間監督の指導法だ。これまで出会って来たどんな指揮官とも違っていた。例えば、仙台での練習では「ミスをしてもいいからチャレンジしろ。ミスしてもいいから、切り替えろ」と言われ、選手同士でもそうやって声をかけあっていたからだ。しかし、ここでは真逆である。
「風間監督は『ミスをするな』って言うんです。『うまいやつはミスをしないし、ミスをしなければ切り替えなんて必要ない』と言う。確かに、と思いました(笑)。今まではミスが当たり前だと思ったし、サッカーはミスのスポーツだと思っていた。でもそう思っていたら、ミスはなくならないし、技術は向上しないんですよね。そういう風に言われたことがなかったので、新鮮でした。ミスをしないで一番良い選択をするというのは、どの指導者よりも要求が高い… 究極ですね。厳しい要求だけど、それでうまくなるし、それを普通にやっていかないといけない」
そして31歳で飛び込んだ環境と刺激を、なぜかお湯に例える。
「熱いお湯に飛び込んで、ちょっと熱過ぎたかもしれない(笑)。最初は、『ちょっと、まだこの温度に慣れへんな… 』と思っていたけど、ようやく慣れて来た。いまはちょっと熱いぐらいになったんで、大丈夫かな」




 京都府の南部に位置する宇治市で生まれた。世界遺産ともなっている平等院鳳凰堂があり、宇治茶で有名な地域である。通っていた小学校の蛇口からお茶が出る以外は、普通の環境だったという。
京都府の南部に位置する宇治市で生まれた。世界遺産ともなっている平等院鳳凰堂があり、宇治茶で有名な地域である。通っていた小学校の蛇口からお茶が出る以外は、普通の環境だったという。
サッカーを始めたのは小学生のときだ。3つ年上の兄の影響で、気づいたらボールを蹴っていた。当時所属していたサッカークラブ「宇治巨椋ボンバーズ」では、とにかくリフティングをたくさんやっていた記憶がある。リフティングを行うことでボールタッチの感覚を養い続け、気づけば1000回以上は軽くできるようになっていた。OBがコーチをつとめていたこのクラブでは、走り込みのようなスポ根的要素の練習は少なく、比較的、理にかなったトレーニングも多かった。
市の選抜に選ばれるような巧い子は、京都パープルサンガ(当時)のジュニアユースに進んでいくのが、この地域のエリートコースだ。角田もご多分に漏れず、このコースを歩んでいる。中学からすでにボランチやセンターバックなど後方のポジションで活躍し、いつしか周囲からも注目を集める存在になっていた。
本来ならば、ここで高校からプロになるまでの道のりを詳しく書いていくのだが、角田のプロデビューは驚くほど早い。2001年5月23日、まだユース所属だった高校生のときにJ2リーグでデビューを果たしている。17歳10ヵ月13日での出場は、当時のJ2最年少記録である。4-0で勝っている状況で、残り10分で出た試合で、しかも相手は川崎フロンターレだ。
高校生の頃からトップチームに帯同していた為、ユースの大会にほとんど出ていない。高校生活の思い出もほとんどなく、「切ないですよ」と笑う。年代別の代表にも主力として選ばれており、2003年のワールドユース選手権(現:U-20ワールドカップ)にも出場。その後は、いわゆる飛び級でアテネ五輪代表候補にも入った。傍目から見ると順風満帆のキャリアのように思えるが、この時期のキャリアについて聞くと、「パッとせず」というフレーズを繰り返した。
「正直、順調じゃないですよ。ワールドユースに出て、その流れでアテネ五輪を目指す代表に呼ばれて。アテネのときは一次予選のときからヨシトくん(大久保嘉人)がいましたね。そこからはあまりパッとせず… アテネのときは名古屋にいたんですけど、あまりパッとしなくて、また京都に戻って… 」
最終メンバーから落選したアテネ五輪以降のキャリアを観ると、名古屋グランパスエイトと京都サンガを往復している。京都から完全移籍で名古屋に行き、出場機会を求めて期限付き移籍で京都に。期限付きだったので、再び名古屋に復帰… もちろん、両クラブから選手として求められているからこその移籍だが、「あまりパッとせず」と口にするからには、何かしら思い当たる原因もあるのだろう。
「勘違いをしていましたね… いや、勘違いではないかな。自分はもっとできるだろう、と思っていたんですよ。ただうまくいかなかった。それに若い時期にありがちで、人の話もあまり聞かなかったし、受け入れるだけの技量もなかった… 自分の考え方を貫き通したかったし、それが正しいと思っていた」

そんな角田にとって、その運命を大きく変えた出来事がある。
それが2011年、ベガルタ仙台への移籍だ。
このとき、角田のもとには、仙台だけではなくセレッソ大阪からもオファーが届いていた。セレッソはACL出場が決まっており、クラブチームで国際大会を経験できることは大きな魅力で、気持ちは仙台よりもセレッソに傾きかけていた。そんな折、京都でコーチをつとめていた森岡隆三に相談したところ、ふと「一回、ゆっくりと仙台の映像も見てみたら?」とアドバイスされた。
セレッソに関しては、クルピ監督で攻撃陣もしっかりと機能しているというイメージを掴めていた反面、ベガルタに関しては、具体的なサッカーのイメージを掴んでいないまま判断しようとしていた自分に気づいた。そこで良い試合、悪い試合、そしてノーマルな試合のDVDを取り寄せてじっくりと試合を見てみることにした。映像を見てみたら、仙台は想像していたよりも悪いチームではなかった。むしろ「自分が頑張れば、真ん中の順位ぐらいにはいけるんじゃないか?」という思いすら湧いて来た。そして心は仙台への移籍を決めていた。もちろん、これが角田誠の運命を大きく変える決断になったのは、言うまでもない。
「今となれば、その決断がよかったと思ってます。もちろん、人生は一回きりだから、セレッソにいったほうがもっとよかったかもしれない(笑)。それはわからないです。でも仙台に行ったことで、いろんなことを経験できましたから。あの震災もそうだし、キャプテンもそう…」
その言葉のあるように、ベガルタ仙台の一員となり、シーズンが開幕した直後に起きたのが、あの東日本大震災だった。
「いまだに覚えてます。仙台は海外でキャンプをずっとやっていて、仙台に帰らず、そのままアウェイで広島との開幕戦を行ったんですよ。それが終わって、やっと仙台に帰れるな。そしてユアスタでのデビュー戦を楽しみにしていたら…」
あの日、チームの午前練習が終わり、彼は滞在していたホテルにいた。まだ引っ越し前で、ホテルで生活をしていたのだ。
「物凄く揺れて、危ないからホテルから出てくださいと言われた。でも行くところがないので、とりあえずクラブの選手寮に行きました。『明日、試合はどうなるんやろう?』と話していたら、クラブスタッフから『明日の試合は中止になりました。練習するかどうかは、また連絡します』と告げられた。『じゃあ、試合は明後日なのかな』と思っていたぐらい何も情報がなかった」
停電でテレビはつかず、情報源はラジオだけ。選手寮ではユースの高校生や新人だった武藤雄樹(現:浦和レッズ)などの若手と布団を敷いて食堂で寝泊まりしていた。車を運転して、率先して米や食料も買いにいった。余震が多く、そのたびに外に避難する生活が続いた。テレビが映り始めたのは、震災から4〜5日後である。そこでようやく大震災の全貌を把握した。建物は半壊し、大津波の映像を目の当たりすると、「信じられへん…」と絶句するしかなかった。
数日後、チームは一度解散する旨がスタッフから伝えられた。ただ実家に帰ろうにも、飛行機はどこも満席。携帯電話のわずかな充電で友人に連絡し、山形の空港にある関西の便が奇跡的に取れてなんとか京都に帰ることができたが、眠りについても、緊張からすぐに目が覚めてしまう症状がしばらく続いた。
その後、Jリーグ開催の目処が立ち、チームは集合。再集結した3月28日には、チームがバスを借りて、スタッフも含めた総勢48人で石巻を訪問している。
「街がなくなっている光景を見ました。正直、見るのはいやだったんです。悲惨な状態だったので、あまり見たくなかった。でも、あれは感じるものがありました。それに自分たちが行ったら、『ベガルタ、頑張ってください』と応援してくれた… あれは、グッときました」
仙台では練習ができないため、千葉で約3週間、トレーニングを行った。リーグ再開初戦の場所は等々力競技場。相手は川崎フロンターレである。


角田はこの試合に先発出場している。川崎は、中盤のパスカットから始まった攻撃を繰り出し、最後は田中裕介が決めて先制。あの場面、パスミスをした仙台の選手は角田である。試合は仙台が2対1での劇的な逆転勝利をおさめているのだが、試合のことを聞いても、角田本人の記憶は曖昧だ。
「自分のボールを奪われたのは覚えているんですよ… イナさん(稲本潤一)に取られたんですよね。ただ試合のことはほとんど覚えていないんです… 太田と鎌田が決めたのは覚えているけど、とにかく必死だった。みんなが頑張った結果だけど、最後に逆転したのは奇跡だと思います。サポーターも多かったし、すべてのパワーが乗り移った試合じゃないかな… フロンターレはやりにくい試合だったと思います」
鮮明なのは、その後の出来事のほうだ。夜に試合映像を見直したら、試合後のTVインタビューで手倉森監督が号泣していたからである。その姿に思わずもらい泣きをしていた。
「あんなに強い人が、試合後に涙を流していた。手倉森さんは僕らの前では気丈だったし、常にポジティブなことしか言わなかったんです。『サッカーのありがたみを感じろ。自分らのためじゃなくて、被災した人たちのために戦え』と、ずっと言っていた。千葉でキャンプしているときも、『貸してくれる人に感謝しろ』と言い続けていた。あの人が涙を流していたので… 」
角田にとって、手倉森監督から受けた影響はあまりに大きい。
「あの人の人間味ですね。考えさせられるほど言葉が多かった。例えば、『勝って謙虚に、負けて落ち込まず』。若い頃の自分は負けた時はすごくイライラしていたけど、そこであまり落ち込まなくなりました。それに2年目、3年目になると震災のことを忘れそうになる瞬間もあるんです。でも常に『復興の為に』という言葉を言ってくれて、それで思い出すことができた。サッカーの技術はそこまで教わってないんですが(笑)、人間性がサッカーにも影響すると気づきました。できれば、もう少し若い頃に手倉森さんに出会いたかったです」
そんな手倉森監督に率いられたベガルタ仙台は、快進撃を見せる。この年はリーグ戦4位、翌年には優勝争いを繰り広げて2位で終えた。ベガルタ仙台の守備の中心には、いつも角田誠がいた。
「チームとしてまとまっていたし、自信がありました。みんな充実していたし、接戦の試合に勝てた。そうやって勝ち慣れていたのが大きかった。僕自身は、まずは自分が楽しまなあかんと思ってました。誰かの為にと言われても、どういう風にプレーしたら良いのかはわからない。自分が必死にやること。自分が必死さを出すことで、周りの人が何かを感じてくれる。そういう気持ちでやってました」
仙台ではキャプテンマークも巻くようになっていた。もはやチームに欠かすことのない存在になっていたが、角田本人はこの環境に満足していたわけではなかった。在籍3年目、4年目ぐらいから「何か違う」という感覚も少しずつ芽生えて来たという。
そんな4年目のシーズン終盤、川崎フロンターレから獲得オファーが届く。ホーム最終戦で徳島ヴォルティスに勝利し、仙台の残留が決まると、これで仙台での仕事は終わったと自然と思えた。そこに、迷いはなかった。
「今回の移籍に関しては、難しい決断ではなかったです。自分の中でフロンターレはビッグクラブ。仙台に少し物足りなさも感じていたので、また挑戦したいと思ってました。31歳でなかなかこういうチャンスはないかもしれない。もちろんプレイヤーとしても高めてもらったし、あの経験が川崎にもつながっている。本当に仙台には感謝しています」
東日本大震災の復興に関して、仙台と川崎の絆は深い。仙台で主将をつとめていた角田がこのクラブに来るのも、何かの縁なのかもしれない。
 「仙台にいたときからフロンターレがいろいろとやってくれていたのは知っていました。震災のときも一番始めにフロンターレが行動してくれましたよね。それがきっかけかどうかはわからないけど、サポーター同士の仲が良いのも聞いていました」
「仙台にいたときからフロンターレがいろいろとやってくれていたのは知っていました。震災のときも一番始めにフロンターレが行動してくれましたよね。それがきっかけかどうかはわからないけど、サポーター同士の仲が良いのも聞いていました」
両クラブのサポーター同士の絆は言わずもがなで、その証拠に川崎フロンターレに移籍して来た角田誠の応援歌は、仙台時代のものがほぼそのまま受け継がれている。
川崎のコールリーダー・小俣海人氏によれば、応援歌の継承は異例だという。もちろん、仙台サポーターからの依頼もあり実現したものだ。コアサポーターからは「リーダーシップがあり良い選手なので、川崎でも上手くいくと思う」という太鼓判も受けたそうである。メロディはそのままに、仙台の良さを残しつつストレートに伝わる歌詞にアレンジされた。サポーター同士で親交のある川崎と仙台らしいエピソードといえるだろう。
最後に。今回の取材で、角田誠にどうしても聞いてみたいことがあった。それは、自身の応援歌の歌詞にもある「「運命(さだめ)」についての思いだ。悩んだ末に選択したベガルタ仙台に来た直後に東日本大震災で被災した角田誠にとって、運命とは一体何なのか。それをどうしても聞いてみたかったのだ。
彼は「大きい決断をするときは、それを信じるしかないですよね」と胸を張った。あの東日本大震災の時、角田は自分の運命を恨んだかもしれない。移籍先の選択に、強い後悔の念を抱いた瞬間があったことを否定しなかった。だがあの経験が、現在につながっているのも確かである。今ではそう捉えるようになったという。
「もし違う人生だったらと思ったり、あのときに違う選択をしていたら… 昔はそういうことをよく思っていました。でも、そう思う前に、『後悔しない生き方をしよう』と思うようになりました。歳を重ねるにつれて、それを受け入れるしかないと思うようになった。要するに、決断力に自信がなかったり不安だったから、昔はそう思っていたんでしょうね。
例えば、仙台との契約がまだ残っている中で、フロンターレに来た。うまくいかないときは、仙台にいたほうが… って思うこともあるかもしれない。でも、そう思わないような日々を過ごしたい。決断したのだから、そう考えていくと思います。そういうのをひっくるめて今ですから、それをすべて受け入れています。いろんな経験があったからこそ、いま川崎にいると思っている。ちょっとずつ、人間としての自信がついてきたのも大きいのかな」
──角田誠、31歳。
決断して起きる現実をすべて受け入れながら、未来の活路を見出していく。それが、自分の運命なのだから。


profile
[かくだ・まこと]
ベガルタ仙台より完全移籍で加入した経験豊富なDF。ボランチやセンターバックでプレーし、強いフィジカルを生かした厳しいチェックで対戦相手の攻撃の芽を摘む。「毎試合、全身全霊でプレーしたい」との言葉が示すように、泥臭く体を張ってチームのために戦ってくれるだろう。守備陣を統率するキャプテンシーにも期待したい。
1983年7月10日/京都府、
宇治市生まれ
ニックネーム:カク
- ゲーム記録・速報
- 2016シーズン・ゲーム記録
- 最新のゲーム記録・速報
- Jリーグ
- ヤマザキナビスコカップ
- 天皇杯
- Jサテライトリーグ
- 過去のゲーム記録
- 練習試合
- チケット・観戦
- チケット・観戦トップ
- チケット購入ガイド
- スタジアム観戦ガイド
- スタジアム改築
- アウェイツアー日程・申込み
- スケジュール
- トップチーム月間スケジュール
- J1リーグ-1st
- J1リーグ-2nd
- ヤマザキナビスコカップ
- 天皇杯
- サテライトリーグ
- 店舗/各事務所のスケジュール
- 選手・スタッフ
- 2016(最新)
- 2015
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- ファンクラブ
- 後援会のご案内トップ
- 入会特典
- 入会方法
- 後援会とは
- 会員規約集
- 後援会へのお問い合わせ
- スポンサー
- スポンサーのトップ
- スポンサーリスト
- サポートカンパニーご案内
- 川崎フロンターレ持株会
- スポンサーシップ
- ユーティリティ
- ふぁんメール
- ご意見・ご感想・ご要望メール
- 利用規約
- 著作権について
- プライバシーポリシー
- ユーティリティ
- ご意見・ご感想・ご要望
- 利用規約
- 著作権について
- プライバシーポリシー
- クラブプロフィール
- 日本語
- English
- Portuguese
- Vietnamese
- 한국어h
- 繁體字
- 簡体字
- ภาษาไทย